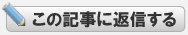119ページ中53ページ目を表示(合計:593件) 前の5件 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | ...119 次の5件
- タイトル
- 投稿日
- 返信数
- なっとく度
- 偏差値があてにならない理由 (0)

- 14/12/06 23:12
- 0 件
- 0 / 0 ( 0% )
- 入試問題は大学からのラブレター (0)

- 14/12/06 23:07
- 0 件
- 0 / 0 ( 0% )
- 過去問の掟 八か条 (0)

- 14/12/06 23:04
- 0 件
- 0 / 0 ( 0% )
- 受験勉強の6ステップ (0)

- 14/12/06 23:00
- 0 件
- 0 / 1 ( 0% )
- 面接・小論文対策もばっちり (0)

- 14/12/06 09:20
- 0 件
- 2 / 4 ( 50% )
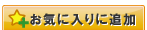
投稿者:東京学力会への さん
14/12/06 23:12
母集団が違う
偏差値はその母集団内の対象者の位置を示すもの。同じ偏差値60 でも、普通の模試と東京大模試では意味がまったく違う。
試験科目や配点が違う
実際の入試と試験科目や配点が大きく違う場合、偏差値を出しても大学ごとに対応した数値にはならないのであまり意味はない。
出題形式が違う
たとえばマーク式と記述式では解法もペースも違う。出題形式や問題数・難易度などが違うと偏差値は正確なものにはならない。
出題範囲・傾向が違う
国語の古文・漢文、英語のリスニングなど、大学ごと出題範囲も出題傾向も違う。偏差値が低くてもこれらに対応できれば断然有利。
実力が発揮されたとは限らない
体調不良や緊張などで実力が発揮できなかったのかもしれない。これらは場慣れしたり、試験時間術を学べば克服できる。
実力の伸びが考慮されていない
「現役生のC判定はA判定相当」といわれるように、偏差値は今後の伸びを考慮していない。学力が伸びる工夫をすればよいのだ。
偏差値を見る際に意識すべきこと
あるテストで偏差値70 をとったとする。これってすごいことなのだろうか? もしそれが算数の九九のテスト結果で満点でなかったのなら、偏差値70 でも非常に残念な結果だ。もしそれが東京大合格者が受けた試験の偏差値なら、偏差値50 でも東京大平均なのだから相当な数値だということになる。偏差値を見る際には母集団の性格を意識することが大切だ。
だから、受験者が違う模試の偏差値を比較してもあまり意味はないし、模試ごとに大学の偏差値が違うのも当然のことなのだ。
偏差値とは、その試験で対象者が集団の平均からどれだけ隔たっているのかを示すもの。実際の入試と母集団も試験内容も違う模試での偏差値は目安程度にしかならないので注意が必要だ。
なっとく!
いまひとつ
この記事を違反報告する
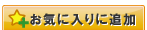
投稿者:東京学力会へのお得情報 さん
14/12/06 23:07
過去問で志望校の傾向を把握する
過去問を何校分も見ていると、それぞれに傾向があるのがよくわかる。大学は入試の問題を通して「こういう人が欲しい」とアピールしているわけだ。それに対して受験生は解答用紙を通じて「私はこういう人です」と大学に返事を送る。入試は大学と受験生との間に交わされるラブレターなのだ。
まだ志望校の過去問を見ていない人はすぐに過去問集を用意して、試験科目や配点はもちろん、出題傾向や問題の数・難易度・試験時間などを調べてみよう。この際、第二志望校や併願校の過去問も一緒に調べておくこと。試験科目や出題傾向がまるで違う場合、併願校のためだけの勉強を考える必要があるからだ。
過去問を調べたあと受験戦略の6ステップを見直して、必要なら修正をかけていこう。
本番同様に解答して実戦力を身につける
インプット・アウトプット学習を終えた科目については、過去問攻略に移っていこう。この際時間を計り、試験時間術を活用して本番さながらに解答すること。一定時間で問題を見切ったり、部分点を集めて得点を伸ばす技術も過去問解答で身につけてしまうのだ。
採点には時間をかけること。解法が複数ある場合はもっとも合理的な方法で解けるよう確認しておこう。部分点は先生に見せて確認してもらうのもよい。答案の書き方ひとつで得点が変わるので、そのエッセンスを学びとるのだ。
センター試験後は志望校の過去問中心の勉強になるが、得意科目についてはできるだけ早い時期にこの実戦解答に入っておきたい。入試までに、全科目少なくとも10 年分は解くようにしよう。
なっとく!
いまひとつ
この記事を違反報告する
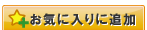
投稿者:東京学力会へのお得情報 さん
14/12/06 23:04
問題から大学が求めているものを読みとる
入試の問題の傾向を読みとれば、大学の思想や必要としている人物像がある程度読みとれる。過去、入試の傾向を変えているような場合でも、その前後の問題を比べれば、変更した理由がわかってくるはずだ。漠然と過去問を解くのではなく、大学と対話するつもりで真剣に接しよう。
予想問題集は過去問以上に活用する
予備校などで出している予想問題集や大学別模試の過去問集は、専門家がその大学の傾向はもちろん、ここ数年の時流や出来事さえ考慮して作り上げたもの。過去問集と同等かそれ以上の価値があるので、入試までに必ず解いておこう。傾向の似た大学の過去問集を解くのもよい。
全問を理解する必要はまったくない
過去問には超難問も含まれている。こうした問題に接した際に重要なのは、解けるべき問題なのか、解けなくてもよい難問なのかを見切れるようになることだ。超難問は時間をかけて理解しようとせず、とれそうな部分点と見切る方法・見切る場所を確認してよしとしておこう。
自己採点を行って部分点のとり方を学ぶ
記述式の場合、必ず自分自身で部分点を採点すること。部分点が把握できれば本質理解に近づくし、部分点がとれる解答用紙の作り方も学べるのだ。採点に不安があったら先生に見てもらって採点方法を教えてもらおう。友だち同士で採点し合い、理由を討論するのもよいだろう。
過去問集を複数用意して最高の解法を探し出す
過去問集を比べてみるとわかるが、記述式の場合、本ごとに解答法がかなり違っていたりする。複数の過去問集を比べてよりよい解法を探し出そう。特に英作文や論述問題の場合、正解を比べると大切な部分があぶり出されてきて、問題の本質が理解できることも少なくない。
時間を意識して実戦さながらに解答する
過去問をじっくり解いて理解を深めるのも悪くはないのだが、過去問の数は限られている。本番同様、実戦的に解く訓練をするために過去問は不可欠なので、じっくり解答したいのなら別の問題集を解く方がいいだろう。入試直前に解くために、過去問数年分をとっておくのも手だ。
過去問の傾向を鵜呑みにしすぎない
過去問を見て大学の傾向を把握する作業は大切だが、傾向が変わることもないとはいえないので、鵜呑みにしすぎないこと。多少傾向が変わっても対応できるように、幅広い知識を身につけておこう。また、入試の内容が変わることもあるので、最新の入試情報を常に集めておこう。
第二志望校や併願校の過去問もチェックする
第一志望校はもちろん、第二志望校や併願校の過去問もチェックしておこう。できれば第二志望校や併願校には試験科目や出題形式・出題傾向が似た大学を選びたい。第一志望校の勉強に集中できるし、志望を変えた際にも対応が簡単だからだ。過去問を見てそんな研究もしておこう。
なっとく!
いまひとつ
この記事を違反報告する
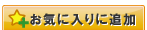
投稿者:東京学力会への良い口コミ さん
14/12/06 23:00
STEP1 全体の流れ・物語を理解する
「理解してしまえば覚えるのは簡単」というように、何より大切なのは内容理解。最初は教科書や簡単な参考書を読み通して、内容理解・全体像把握に努めよう。
STEP2 必要な情報をインプットする
全体の流れ・物語を把握したら不足した知識を入力していく。おおよその理解はすんでいるので、内容の濃い参考書を使って必要な知識を選んで覚えていこう。
STEP3 覚えた知識をアウトプットする
ある程度知識をインプットしたら問題演習に移り、覚えた知識を「問題を解く力」に変えよう。知っていることと問題が解けることは同じではないので要注意。
STEP4 弱点部分の理解・インプットを行う
解けなかった問題は、理解やインプットに戻って弱点を埋めていこう。「理解→インプット→アウトプット→理解→インプット→…」を繰り返すことが大切だ。
STEP5 実力を模試で試す
内容が理解できて問題を解く力があっても合格できるとは限らない。模試で試験時間術などを磨き、プレッシャーに打ち勝つ訓練をして試験に強くなっておこう。
STEP6 過去問で知識を志望校に最適化する
マーク式・記述式で必要とされる能力は違うし、大学・学部ごとに出題傾向があったりする。過去問や予想問題を解き、持っている知識を試験に対応させよう。
理解、インプット、アウトプットの三本柱
受験戦略を駆使することで勉強内容を最小化することはできる。しかし、受験勉強自体はやはり地道に進めていくしか方法がない。 内容を理解していないのに単語や公式を覚えても苦労するだけで使いこなすことができないし、知識を入力しても問題を解いて使ってみなければ使用法も応用法もわからない。
やはり「理解→インプット→アウトプット」を繰り返すのが受験勉強の王道なのだ。
ただし、授業などでひと通り勉強が進んでいる人は、最初から参考書を用いてインプット学習に入ってもいいし、いきなりアウトプット学習を行って、必要な項目だけ理解・インプットに立ち戻る方法もある。いずれにせよ、「理解→インプット→アウトプット」の繰り返しである点は変わらない。
【インプット】
目的:実力養成
方法:まとめノート作り、単語・数値・公式記憶
インプット学習とは、不足した知識を入力していく勉強だ。参考書を丁寧に進めていって、覚えるべき項目をまとめノートなどに書き出して、何度も繰り返し確認して確実に身につけていこう。問題集や模試・過去問などをやる際も、必要となった知識をこのまとめノートに追加して、情報を一元化すると便利だ。
【理解】
目的:基礎力養成
方法:教科書・基礎参考書の通し読み
受験勉強でもっとも大切なのは内容理解。時代背景や基礎文法、公式が導かれる理由といった基本が理解できれば、単語や公式の記憶も難しくないのだ。手をつけていない科目や単元がある人はまず教科書や基礎参考書を読み通し、全体を俯瞰しておこう。この際、覚えることより理解することに力点を置くこと。
【アウトプット】
目的:実戦力養成
方法:問題演習、過去問解答、模試受験
アウトプット学習とは、問題を解くことで覚えた知識を様々な角度から叩き・鍛える勉強だ。理解したと思っていても誤解していることもあるし、入試では知識を応用したり複数の知識を組み合わせたりして解く問題も出題される。次第に問題の難易度を上げていって、最終的に入試レベルに到達するよう調整しよう。
秋からはアウトプット学習を中心に
理解・インプットの学習は外せないが、これらはできるだけ早めにすませ、秋からはアウトプット中心の学習に移行したい。知識を実戦向けに鍛え上げる必要があることと、差がつきやすい思考型問題になるべく時間を使うためだ。
たとえば現代文や数学の答えを記憶してもほとんど意味がない。なぜその公式を使うのか、なぜそのように解答するのかを理解して、次に類題を見たときに自然に解くことができるように訓練しなければならないのだ。このような思考型問題で重要なのは「解答の導き方」を学ぶこと。そのためにはやはり繰り返し問題を解く必要がある。そして最後に過去問を解き、入試での得点力に変えるのだ。
なっとく!
いまひとつ
この記事を違反報告する
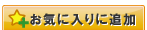
投稿者:東京学力会へのお得情報 さん
14/12/06 09:20
私が受験した公募制推薦では面接と小論文試験がありました。面接に対しては元々苦手意識があったのですが、何度もチューターに練習していただいたおかげで、徐々に自信を持てるようになりました。
小論文も、短く書く練習から始め、完璧な文はなかなか書けませんでしたが添削していただいて書き直してということを何度も繰り返すことで色々なテーマに対応できるようになり、本番でも焦らずに書ききることができました。
面接や小論文は高校で対策をしてもらっている子が多かったのですが、人数が多い分あまり見てもらえなかったようなので、東京学力会で対策していただけた事はとても有難く、合格に大きく近づけました。
なっとく!
いまひとつ
この記事を違反報告する
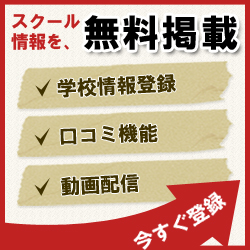
ようこそゲストさん
口コミ掲示板の便利な機能を利用するには会員登録が必要です。
>> [無料] 会員登録
>> ログインする

関連カテゴリ
- ■塾・予備校・家庭教師
- ・学習塾・進学教室別
- ・家庭教師別
- ・予備校別
- ・その他塾・予備校・家庭教師
ご利用案内
- ・運営組織について
- ・利用規約
- ・掲示板の書き込みマナー
- ・リンクについて
- ・お問い合わせ
What's New
- ・カテゴリを追加
- ・スクールを追加
- ・口コミのデザインを変更
- ・携帯サイトの作成サービス開始
スクール運営者様
- ・[無料] スクール登録・学校登録
- ・携帯サイト作成サービス
- ・プライバシーポリシー
- ・広告掲載について
- ・スクール向けログイン
- ・よくあるご質問
- [PR] Redshiftを使ったビッグデータ解析