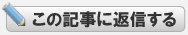28ページ中23ページ目を表示(合計:139件) 前の5件 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ...28 次の5件
- タイトル
- 投稿日
- 返信数
- なっとく度
- 過去問の最効率復習法 (0)

- 14/12/06 23:13
- 0 件
- 0 / 0 ( 0% )
- 入試問題は大学からのラブレター (0)

- 14/12/06 23:07
- 0 件
- 0 / 0 ( 0% )
- 過去問の掟 八か条 (0)

- 14/12/06 23:04
- 0 件
- 0 / 0 ( 0% )
- 面接・小論文対策もばっちり (0)

- 14/12/06 09:20
- 0 件
- 2 / 4 ( 50% )
- 「塾」ではなく「学校」 (0)

- 14/12/03 23:25
- 0 件
- 1 / 1 ( 100% )
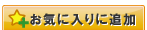
投稿者:東京学力会へのお得情報 さん
14/12/06 23:13
模試・過去問を解く
↓↓↓
採点し、合格最低点に対して何点足りないか計算する
↓↓↓
得点プランを確認し、科目ごとに足りない点数を計算する
↓↓↓
どの問題が解けていれば得点プランに達していたのか確認する
↓↓↓
その問題が解けるようになるよう勉強内容を吟味する
↓↓↓
計画を練り直してスケジュールを再調整する
なっとく!
いまひとつ
この記事を違反報告する
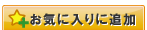
投稿者:東京学力会へのお得情報 さん
14/12/06 23:07
過去問で志望校の傾向を把握する
過去問を何校分も見ていると、それぞれに傾向があるのがよくわかる。大学は入試の問題を通して「こういう人が欲しい」とアピールしているわけだ。それに対して受験生は解答用紙を通じて「私はこういう人です」と大学に返事を送る。入試は大学と受験生との間に交わされるラブレターなのだ。
まだ志望校の過去問を見ていない人はすぐに過去問集を用意して、試験科目や配点はもちろん、出題傾向や問題の数・難易度・試験時間などを調べてみよう。この際、第二志望校や併願校の過去問も一緒に調べておくこと。試験科目や出題傾向がまるで違う場合、併願校のためだけの勉強を考える必要があるからだ。
過去問を調べたあと受験戦略の6ステップを見直して、必要なら修正をかけていこう。
本番同様に解答して実戦力を身につける
インプット・アウトプット学習を終えた科目については、過去問攻略に移っていこう。この際時間を計り、試験時間術を活用して本番さながらに解答すること。一定時間で問題を見切ったり、部分点を集めて得点を伸ばす技術も過去問解答で身につけてしまうのだ。
採点には時間をかけること。解法が複数ある場合はもっとも合理的な方法で解けるよう確認しておこう。部分点は先生に見せて確認してもらうのもよい。答案の書き方ひとつで得点が変わるので、そのエッセンスを学びとるのだ。
センター試験後は志望校の過去問中心の勉強になるが、得意科目についてはできるだけ早い時期にこの実戦解答に入っておきたい。入試までに、全科目少なくとも10 年分は解くようにしよう。
なっとく!
いまひとつ
この記事を違反報告する
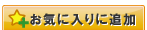
投稿者:東京学力会へのお得情報 さん
14/12/06 23:04
問題から大学が求めているものを読みとる
入試の問題の傾向を読みとれば、大学の思想や必要としている人物像がある程度読みとれる。過去、入試の傾向を変えているような場合でも、その前後の問題を比べれば、変更した理由がわかってくるはずだ。漠然と過去問を解くのではなく、大学と対話するつもりで真剣に接しよう。
予想問題集は過去問以上に活用する
予備校などで出している予想問題集や大学別模試の過去問集は、専門家がその大学の傾向はもちろん、ここ数年の時流や出来事さえ考慮して作り上げたもの。過去問集と同等かそれ以上の価値があるので、入試までに必ず解いておこう。傾向の似た大学の過去問集を解くのもよい。
全問を理解する必要はまったくない
過去問には超難問も含まれている。こうした問題に接した際に重要なのは、解けるべき問題なのか、解けなくてもよい難問なのかを見切れるようになることだ。超難問は時間をかけて理解しようとせず、とれそうな部分点と見切る方法・見切る場所を確認してよしとしておこう。
自己採点を行って部分点のとり方を学ぶ
記述式の場合、必ず自分自身で部分点を採点すること。部分点が把握できれば本質理解に近づくし、部分点がとれる解答用紙の作り方も学べるのだ。採点に不安があったら先生に見てもらって採点方法を教えてもらおう。友だち同士で採点し合い、理由を討論するのもよいだろう。
過去問集を複数用意して最高の解法を探し出す
過去問集を比べてみるとわかるが、記述式の場合、本ごとに解答法がかなり違っていたりする。複数の過去問集を比べてよりよい解法を探し出そう。特に英作文や論述問題の場合、正解を比べると大切な部分があぶり出されてきて、問題の本質が理解できることも少なくない。
時間を意識して実戦さながらに解答する
過去問をじっくり解いて理解を深めるのも悪くはないのだが、過去問の数は限られている。本番同様、実戦的に解く訓練をするために過去問は不可欠なので、じっくり解答したいのなら別の問題集を解く方がいいだろう。入試直前に解くために、過去問数年分をとっておくのも手だ。
過去問の傾向を鵜呑みにしすぎない
過去問を見て大学の傾向を把握する作業は大切だが、傾向が変わることもないとはいえないので、鵜呑みにしすぎないこと。多少傾向が変わっても対応できるように、幅広い知識を身につけておこう。また、入試の内容が変わることもあるので、最新の入試情報を常に集めておこう。
第二志望校や併願校の過去問もチェックする
第一志望校はもちろん、第二志望校や併願校の過去問もチェックしておこう。できれば第二志望校や併願校には試験科目や出題形式・出題傾向が似た大学を選びたい。第一志望校の勉強に集中できるし、志望を変えた際にも対応が簡単だからだ。過去問を見てそんな研究もしておこう。
なっとく!
いまひとつ
この記事を違反報告する
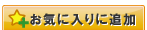
投稿者:東京学力会へのお得情報 さん
14/12/06 09:20
私が受験した公募制推薦では面接と小論文試験がありました。面接に対しては元々苦手意識があったのですが、何度もチューターに練習していただいたおかげで、徐々に自信を持てるようになりました。
小論文も、短く書く練習から始め、完璧な文はなかなか書けませんでしたが添削していただいて書き直してということを何度も繰り返すことで色々なテーマに対応できるようになり、本番でも焦らずに書ききることができました。
面接や小論文は高校で対策をしてもらっている子が多かったのですが、人数が多い分あまり見てもらえなかったようなので、東京学力会で対策していただけた事はとても有難く、合格に大きく近づけました。
なっとく!
いまひとつ
この記事を違反報告する
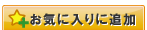
投稿者:東京学力会へのお得情報 さん
14/12/03 23:25
高校時代、成績が芳しくなかった私は、東大は難しいので、志望校変更を先生に勧められたこともあったのですが、東京学力会ではそんなことはいっさいありませんでした。チューターに言われたことは「120 %の力を出しましょう」でした。今になって冷静に考えると、120 %の力でないと合格できないということだったのかもしれませんが(笑)、その時はやる気が起こったものです。センター試験の成績が不調で悩んでいた時も、チューターが「僕は、君が絶対東大に受かるなんて言わないよ。でも、君がこの1年、少なくとも地理に関しては、東大に受かるだけの努力をしてきたことを、僕は世界中の人間に証言できるよ」と励ましてくださいました。ずっと自分を見ていてくださったんだなあ……。その視線に恥じないように、最後まで全力で駆け抜けようと、思いを新たにしました。「 東京学力会のチューターは入試のプロだ。」と、とても信頼できましたが、ただそれだけでなく、予備校なのに受験至上主義ではなくて、とても人間くさく、愛情が感じられました。私にとって東京学力会は「塾」ではなく「学校」だったのです。
なっとく!
いまひとつ
この記事を違反報告する
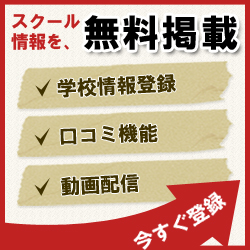
ようこそゲストさん
口コミ掲示板の便利な機能を利用するには会員登録が必要です。
>> [無料] 会員登録
>> ログインする

関連カテゴリ
- ■塾・予備校・家庭教師
- ・学習塾・進学教室別
- ・家庭教師別
- ・予備校別
- ・その他塾・予備校・家庭教師
ご利用案内
- ・運営組織について
- ・利用規約
- ・掲示板の書き込みマナー
- ・リンクについて
- ・お問い合わせ
What's New
- ・カテゴリを追加
- ・スクールを追加
- ・口コミのデザインを変更
- ・携帯サイトの作成サービス開始
スクール運営者様
- ・[無料] スクール登録・学校登録
- ・携帯サイト作成サービス
- ・プライバシーポリシー
- ・広告掲載について
- ・スクール向けログイン
- ・よくあるご質問
- [PR] Redshiftを使ったビッグデータ解析