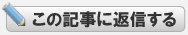28ページ中25ページ目を表示(合計:139件) 前の5件 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 次の5件
- タイトル
- 投稿日
- 返信数
- なっとく度
- まず行動を起こすことが肝心 (0)

- 14/10/23 10:39
- 0 件
- 0 / 3 ( 0% )
- 特徴 (0)

- 14/10/18 23:40
- 0 件
- 2 / 10 ( 20% )
- AO入試とは (0)

- 14/09/02 16:36
- 0 件
- 2 / 7 ( 29% )
- 高校1年生へ (0)

- 14/08/28 23:56
- 0 件
- 2 / 7 ( 29% )
- とても親身 (0)

- 14/08/25 11:59
- 0 件
- 8 / 13 ( 62% )
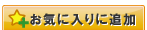
投稿者:東京学力会へのお得情報 さん
14/10/23 10:39
まだ将来の夢が明確に定まっていない人もいるでしょう。私も、高校時代、何をやりたいのか、漠然としていた気がします。そんな時に大切なのは、自分で調べるだけでなく、先生や友人たちに相談し、その意見に真摯に耳を傾けることだと思います。自分一人で考えていると、どうしても考えが狭まってしまうからです。そうした相談ができる人脈を築くことが重要です。
もう1つ大切なポイントは、ちょっとでも興味を持ったら、それを学ぼうという行動を起こすこと。もちろん、失敗することもあるでしょう。いざ飛び込んでみたら、自分には適性がないことがわかったり、すぐに興味を失ってしまったりすることもあるかもしれません。けれども、その時点でいくらでも軌道修正はできます。私自身の経歴がそれを証明しています(笑)。夢とは最初は漠然としたものでいい。その夢を目標に変えるためには、まず行動を起こすことが肝心。そう私は考えています。
なっとく!
いまひとつ
この記事を違反報告する
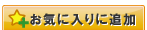
投稿者:東京学力会へのお得情報 さん
14/10/18 23:40
レベル別のクラス編成ですから、もっと高度なところからスタートするクラスもあったと思いますが、私は全教科とも最も下のクラスを選択したので、基礎の基礎から学ぶことができました。
それでも、当初は全く理解できない状態で、先生に相談しました。今、考えると、そんな生徒に対しては「しっかり予習して授業に臨みなさい」とアドバイスするのが一般的だと思います。ところが、東京学力会の先生方は、「一学期は予習をしなくていい」と言われました。そんな先生に出会ったのは初めてでした。「学力がゼロの今の段階で、予習をやっても苦痛なだけ。全部授業の中で補うから、一学期までは復習を完璧にやりなさい。そうすれば夏以降には必ず理解できるようになる」という言葉に感動して、復習に専念しました。
しかも、東京学力会では、一人ひとりに応じたサポートも行われていました。先生に「この部分がわからない」と質問に行くと、「では、その部分の解説のプリントを作るから」と言われ、次の日には実際にそのプリントが渡されます。「プリントを読んでもわからなかったら、いつでも質問にきなさい」と。個別のプリントを作成するのは、大変な労力だったと思いますが、そうしたスタンスが東京学力会の先生方の大きな特徴です。
なっとく!
いまひとつ
この記事を違反報告する
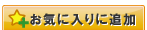
投稿者:東京学力会へのお得情報 さん
14/09/02 16:36
AO入試は学力試験だけでなく、面接・小論文や書類審査、自己PRなどで、受験生の個性や適性、意欲など総合的な人物評価を行う選抜方法だ。
高校長の推薦を必要としない場合が多く、専願の大学が大半。このため、自分が本当に入学を希望する第一志望校かどうかを見極めなければならない。
また、AO入試は選考が長期間にわたるため、最終的に不合格になった場合に備え、推薦入試や一般入試の準備もしておいたほうがよい。
AO入試の出願条件は、推薦入試と同じく学業成績、現浪、併願の可否などである。
学業成績は、難関大などを除き、全体的には私立大を中心にかなり緩やかなのが実状だ。
なっとく!
いまひとつ
この記事を違反報告する
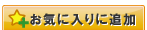
投稿者:東京学力会へのお得情報 さん
14/08/28 23:56
自分の勉強方法を以下の質問を読んで当てはまるものに○を付けよう。○がいくつあるかな?
1.予習・復習は忘れずにやった。
2.宿題は必ずやり、提出も守った。
3.授業中にノートには板書だけでなく先生の言葉も書いた。
4.授業でわからないところは即先生に質問した。
5.定期テストや模擬試験で間違えた箇所は必ず復習した。
6.「なぜだろう?どうしてだろう?」っていう意識で問題・授業に取り組んだ。
7.規則正しい生活リズムを保っていた。
8.目標を持って中学生活を送った。
○が6個以下だったら、間違いなく定期テスト前の一夜漬け、つまり、暗記に頼った勉強が中心だったのではないかな? これでは、仮に得点は取れたとしても、知識として積み重ねることはできない。もちろん暗記しなければならないことは山ほどあるが、勉強の基本とは、疑問点を解決するために、解答を導き出すプロセス(過程)を理解することにあるのだ。
つまり、筋道立てて物事を考える力(論理的思考能力)をつける必要がある。そしてある事柄を知識として身に付ける方法は、
「疑問 → 質問 → 理解 → 演習 → 知識の定着」
である。詳しく説明するよ。
疑問点が出たら、まずは自分で頑張ってみる(自力で解決できる能力を養えるぞ)。
どうしてもダメだったら、チューターに質問に行く。いろいろ説明してもらったあと、理解できたところで、まだ終わりじゃないよ。その理解できた箇所を演習(問題集などで問題練習)するのだ。それを繰り返せばその知識は絶対に定着するようになる。
よくあるのは、「基礎力あるつもりなのですが、模試になると得点できないんです。」
これは、理解できたところで「あっ分かった!! じゃあ次の問題にいくぞ。」って、一番重要な演習(問題練習)を繰り返していないことが原因なのだ。
これでは理解は出来ても、知識として定着しないから、同じ問題でも形を変えられたときには対応できないし、応用力なんて身に付くはずがない。だから模試で得点できないのだ。さあ、高校時代は是非このプロセスを重視する勉強習慣を身につけよう。
それと、もうすでに、幼稚園の先生になりたい、医者になりたい、建築家になりたい、などと進路がハッキリ決まっている人もいることだろう。一方で、なかなか決められないという人もいると思うが、もちろん焦ることは全くない。こんなに情報が入り乱れている世の中だから一つに決めるのが難しい時代でもある。ゆっくり決めていこうよ。
進路を決めるためにまずやってみることは、自分はどんな職業に向いているかを考えてごらん。身近にある職業や、家族・親せきの人が就いている職業などを自分がやったらどうだろうと仮定して、自分に向いているかどうかを考えてみるのも良いね。
また、君の高校でどんな職業に向いているかを判定する「職業適性テスト」のようなものをやるだろうから、それも参考にしたらどうだろう。気になる職業があったら、そのつど、その職業に就くために適している進路は、大学か・短大か・専門学校か…を調べ、その学校が開催するオープンキャンパス(「オーキャン」と略して使おう。「学校説明会」と同意語)や体験授業(実際に大学や専門学校の授業に参加できるイベント)に参加してみよう。これを繰り返すことで、徐々に職業や進路(学校)が絞れてくるはずだ。
勉強方法のこと、授業内容のこと…、さらに高2の後半頃からは、進路のこと、受験勉強のこと、過去問の対策のこと、または生活面全般のこと… いろいろな悩みが出てくるものである。
でも、そんな時に頼りになるのは、家族の人たちや友人ももちろんだが、やはり担任やチューターの先生たちだ。
「ここが理解できないんですが……」と授業の質問や、「この分野が苦手なので、何かプリントをくださいますか」と自学自習を助けてもらったり、「時間の使い方が上手くできないんです」と生活習慣のアドバイスをもらったり、「将来やりたいことが決まらなくって…」「勉強はしているんですが、模試で結果が出ないんです」「志望理由書(小論文)の添削をしていただけませんか」「過去問をやればやるほど不安になっています」「志望校がなかなか決められません」など進路全般に関する悩みを相談する際に、先生たちを積極的に“利用”しまくっちゃいましょう。
日頃から常に先生たちと関わることで、キミと先生との間で堅固な信頼関係を築くことができれば、進路目標にもどんどん近づいていけるし、何より本当に充実した3年間を過ごすことができるはずだ。
なっとく!
いまひとつ
この記事を違反報告する
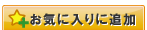
投稿者:東京学力会へのお得情報 さん
14/08/25 11:59
先生がとても親身になってくれることが、なんといっても、この学校の一番の魅力です。
普段から、「わからないところはありませんか?」「何でも相談にきてね」などと声をかけてくださるので、疑問があればいつでも気軽に質問できます。
SRでも、1対1できっちりつき合ってくれる、とても良い先生ばかり。しかも学習内容についてはもちろん、生活での悩みなどもたくさん聞いてくれるほど距離が近く、一緒に泣きながら話をしてくださったこともあります。
なっとく!
いまひとつ
この記事を違反報告する
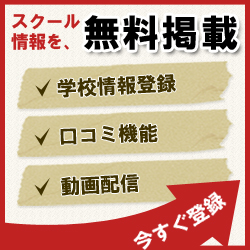
ようこそゲストさん
口コミ掲示板の便利な機能を利用するには会員登録が必要です。
>> [無料] 会員登録
>> ログインする

関連カテゴリ
- ■塾・予備校・家庭教師
- ・学習塾・進学教室別
- ・家庭教師別
- ・予備校別
- ・その他塾・予備校・家庭教師
ご利用案内
- ・運営組織について
- ・利用規約
- ・掲示板の書き込みマナー
- ・リンクについて
- ・お問い合わせ
What's New
- ・カテゴリを追加
- ・スクールを追加
- ・口コミのデザインを変更
- ・携帯サイトの作成サービス開始
スクール運営者様
- ・[無料] スクール登録・学校登録
- ・携帯サイト作成サービス
- ・プライバシーポリシー
- ・広告掲載について
- ・スクール向けログイン
- ・よくあるご質問
- [PR] Redshiftを使ったビッグデータ解析